
火が描く香りのお茶「釡炒り茶」九州に受け継がれる希少な一杯。
特集「炒るお茶、蒸すお茶。」目次
釜炒り茶の製法
摘み取った茶葉を鉄佂で炒ることで殺青。300度以上の鉄釜を使い、手あるいは炒葉機で撹拌(かくはん)しながら、茶葉に均一に火を通していく。その後は茶葉の水分を均等にするため揉み込む「揉捻(じゅうねん)」の工程へ。この時、くるりと捻(ねじ)れて丸まった勾玉状になるのも、釜炒り茶の特徴。熱風や直火を当てて乾燥させる「水乾」、乾燥させながら勾玉状で締まりのある茶葉に整える「締め炒り」、丸まった形の茶葉は乾きにくいのでさらなる「乾燥」を経て、仕上げていく。
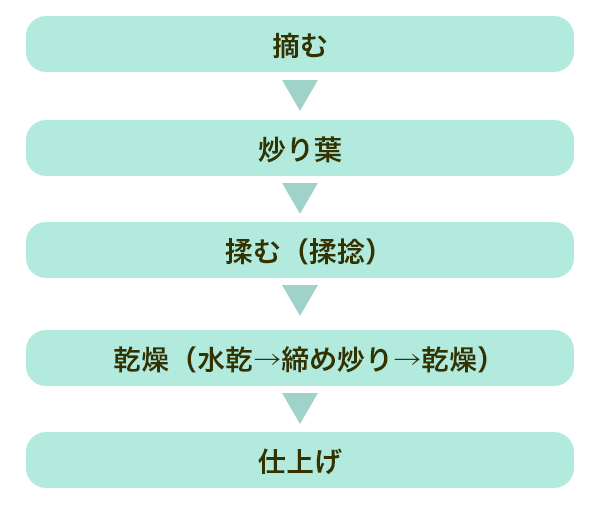
火と技が育んできた釡炒り製法という1%の軌跡
茶葉を炒り、揉み、乾かす――。釡炒り茶は、文字通り鉄製の「釡」で摘みたての茶葉を炒るところから始まります。300度を超える高温の釡で、茶葉一枚一枚に均一に火を入れていく、繊細で丁寧な製法です。
炒られた茶葉は、ふわりと芳ばしい香りをまといます。これが釡炒り茶ならではの「釡香(かまか)」です。軽やかで澄んだ味わいとともに、お茶の原点を感じさせてくれる一杯です。
釡炒り茶の製法は中国から九州に伝わったとされています。古くから中国との交流が盛んだった九州は、新しい技術や文化がいち早く伝わる土地でもありました。また、大がかりな設備を必要としない釡炒り製法は、山深い農村にも広まり、各地で独自の工夫を加えながら受け継がれてきました。
現在では九州の中でも佐賀、熊本、宮崎3県の山間部が主な産地で、国内緑茶生産量のわずか1%未満という、とても希少な緑茶なのです。
熟練の職人技で炒る宮崎の高地に香るお茶
釜炒り茶の一大産地、宮崎県の五ヶ瀬町に、釜炒り名人の興梠(こうろぎ)洋一さんを訪ねました。標高600mを超える高地に茶畑が広がる光景は圧巻です。

興梠(こうろぎ)洋一さん
「緑碧(ルーピー)茶園 五ヶ瀬茶園」代表。全国茶品評会農林水産大臣賞を17回も受賞するなど、釜炒り茶作り38年の名人。同茶園では2013年に有機JASを取得。釜炒り茶の他、萎凋(いちょう)釜炒り茶、和紅茶、創作茶など、釜炒り茶を伝承しながら、その技術を生かした新たな日本茶も次々と発信している。また、ルピシアのグループ会社「株式会社緑碧茶園」の代表も務め、「北限のお茶に挑む。」プロジェクトも推進。
「この辺は春の訪れが遅くて、他の産地が一番茶を出荷するころにようやく収穫が始まる厳しい環境なんです。朝夕の寒暖差も大きい。でも、だからこそ上質な茶葉が育つと思っていますし、新茶の早さを競うのではなく、味や技術で差別化する風土ができてきたのだと思います。」
釜炒り製法には、熟練の技術と経験が欠かせません。それは昔ながらの手炒りでも、機械製造でも同じこと。完全な機械化が難しい製法のため、その時々の茶葉の状態を見極めながら火入れをしていく作業は、大量生産とは一線を画す、まさに職人技です。
「釜炒り茶は香りがよく立って、渋みと甘みのバランスがいい。飲み疲れしないのが魅力ですね」と、興梠さんは笑顔で語ります。
九州の中でも、なぜ五ヶ瀬町やその周辺に釜炒り茶が受け継がれてきたのでしょうか。
「この辺では代々釜炒り茶を作り、飲んできたから、体に染みついているんでしょうね。『蒸し茶はどうも口にあわんねぇ』って言う人が多くて(笑)。日常茶として暮らしになじんでいる、地域の味ですね」と興梠さん。
釜炒り茶の一杯には、地域の歴史と風土が育んだ物語が息づいています。

さっきまで茶畑に茂っていた、初摘みの茶葉。ふっくらとしてみずみずしい。

石窯に焚べられた薪は真っ赤に燃えあがり、鉄釡の温度は300℃にまでなる。


炒る、嗅ぐ、揉む。五感をフルに使って、茶葉の状態を見極める。

五ヶ瀬茶園の窓から茶畑を望む。雨上がりの湿った空気に、緑葉のグラデーションがしっとりと映える。
特集「炒るお茶、蒸すお茶。」目次

煎茶を極める 伝統の手揉み茶
蒸した茶葉を、加熱しながら5~6時間かけて丁寧に揉み、乾燥させて仕上げる「手揉み製茶」。濃厚で芳醇な風味は、熟練の技と長い時間をかけた手間によって生まれます。ルピシアでは、この伝統的な煎茶製法を受け継ぐ、生産量の限られた希少な茶葉を、通信販売限定で8月上旬に発売予定です。
≫ 「伝統の手揉み茶」はこちら
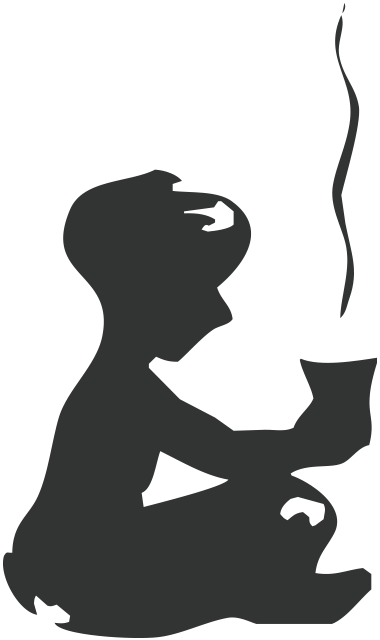 LUPICIA Tea Magazine
LUPICIA Tea Magazine