
緑茶の製法には「炒るお茶」と「蒸すお茶」があるのをご存じですか?
特集「炒るお茶、蒸すお茶。」目次
茶葉を加熱処理する緑茶 その2つの「殺青(さっせい)」技術
日々の暮らしに寄り添い、ほっとできる時間へ誘ってくれる緑茶。あまりに身近すぎて、その種類については意外と知られていないかもしれません。
そもそも緑茶とは、茶葉を発酵させずに製造したお茶の総称です。摘み取ってすぐの茶葉を加熱して発酵を止め、酸化酵素の働きを抑えることで作られます。この工程を「殺青」と呼びます。少し物騒な言葉に聞こえるかもしれませんが、青々とした茶葉の時を止めることで、緑茶という新たな命を紡いでいく 。そんなニュアンスも感じられます。
殺青には2つの方法があります。ひとつは、「火」の力で茶葉の香ばしさを際立たせる「釡炒り製法」。日本では九州を中心に受け継がれている、今では希少な製法です。もうひとつは、「蒸気」の力で茶葉の色鮮やかさを残して風味を豊かに表現する「蒸し製法」。現在、日本の緑茶の主流となっている製法です。日本の緑茶はこの「炒るお茶」と「蒸すお茶」に大別され、それぞれ異なる魅力を持っています。

雨上がりの茶畑に映える新葉。6月を目の前に、いよいよ初摘みが始まった。

中国から伝来した「炒るお茶」
日本で進化普及した「蒸すお茶」
炒るお茶「釡炒り茶」のルーツは中国にあります。明の時代(1368〜1644年)、釡で茶葉を炒って仕上げる緑茶の製法が生まれ、発展しました。中国茶といえば、日本では烏龍茶などの半発酵茶がよく知られていますが、実は中国で最も多く生産・消費されているのは、この釡炒り緑茶なのです。
この製法が日本に広まったのは江戸時代初期。1654年、明から来日した高僧・隠元によるものと伝えられています。長崎の中国寺院「興福寺」に招かれた隠元はその住職となり、後に江戸幕府の支援の下、京都宇治に「萬福寺」を創建。釡炒り茶の製法だけでなく、精進料理や建築様式など、多くの明文化を日本にもたらしました。
一方で、もう少し時代をさかのぼった室町時代後期(1500年ごろ)にも、佐賀に渡った中国の陶工が、釡炒り茶の製法を伝えたとされています。どちらの説にも共通するのは、九州という風土と人々の営みの中で、この製法が受け継がれてきたということです。
時代を進めて、江戸中期。京都の茶商・永谷宗円は、まったく新しい試みに挑みます。それが「青製煎茶製法」と呼ば
れる蒸し製法によるお茶の原型です。茶葉を蒸して発酵を止める方法は、かつて中国の緑茶でも使われていましたが、中国ではやがて釡炒り製法が主流に。日本ではこの蒸し製法が独自に進化、発展していったのです。
蒸すお茶は次第に全国へ広まり、江戸の町人たちの間にもお茶を楽しむ習慣が浸透していきました。明治以降には製法の機械化・大量生産も進み、現在では、日本の緑茶の9割以上が蒸し製法によって作られています。
どちらも深い歴史と人々の工夫が育んできた緑茶の形。その歩みが、現在につながっています。
特集「炒るお茶、蒸すお茶。」目次

煎茶を極める 伝統の手揉み茶
蒸した茶葉を、加熱しながら5~6時間かけて丁寧に揉み、乾燥させて仕上げる「手揉み製茶」。濃厚で芳醇な風味は、熟練の技と長い時間をかけた手間によって生まれます。ルピシアでは、この伝統的な煎茶製法を受け継ぐ、生産量の限られた希少な茶葉を、通信販売限定で8月上旬に発売予定です。
≫ 「伝統の手揉み茶」はこちら
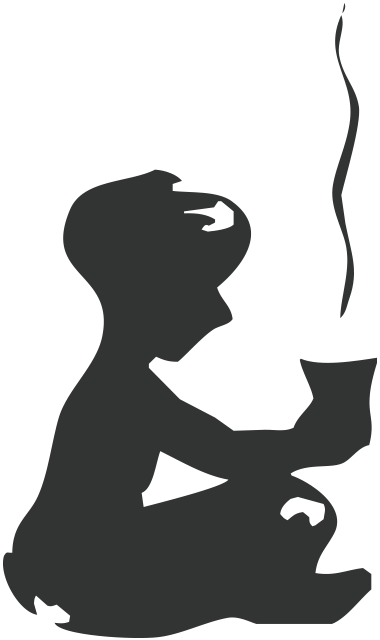 LUPICIA Tea Magazine
LUPICIA Tea Magazine