
多彩な緑茶を生み出した「蒸すお茶」という発明。
特集「炒るお茶、蒸すお茶。」目次
煎茶の製法
摘み取った茶葉が新鮮なうちに、蒸気によって加熱。茶葉に含まれる水分を均一にするため、茶葉を揉みほぐしていく。熱風を当てながら揉む「粗揉(そじゅう)」、加熱せずに揉む「揉捻」、乾燥させながら揉む「中揉(ちゅうじゅう)」、形を整えながら揉む「精揉(せいじゅう)」と、段階に分けて行う。仕上がった茶葉は細く撚(よ)られて針のような形に。乾燥させて「荒茶」が完成する。この後、選別や火入れなどを経て「仕上げ茶」になる。
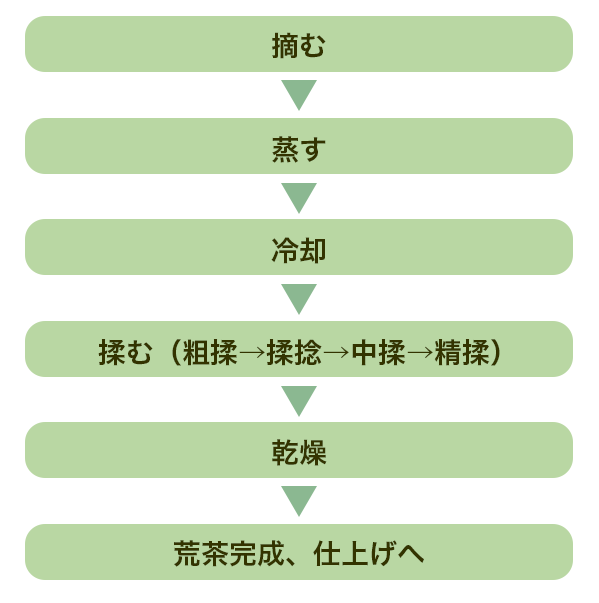
緑茶の味わいを一変
蒸し製法の革命
茶葉を蒸し、揉み、乾かす――。
京都の茶商・永谷宗円による大胆な発想の転換は、緑茶の味わいに革新をもたらしました。日光をたっぷり浴びた茶葉を、高温の蒸気で素早く蒸し、数段階にわたり揉みながら乾燥させることで、茶葉本来の鮮やかな緑色を残し、まろやかな旨みと香り、そして渋みとのバランスが取れた緑茶に仕上がったのです。
この製法で作られる緑茶を「煎茶」と呼ぶようになりました。煎茶の旨みは、だし文化を大切にしてきた日本人の味覚に深く響きました。さらに、生産の現場においても、短時間で均一に加熱できるこの製法は効率が良く、機械化・自動化が進めやすいという利点がありました。こうした背景も、煎茶が全国に広く普及した理由のひとつです。
江戸、明治、大正、昭和へと社会が目まぐるしく変わる中、煎茶の広がりには飲む人と作る人、それぞれのニーズが自然と重なっていった、そんな流れがあったのかもしれません。
多彩な味わいを表現
蒸し時間が生む個性
煎茶は元々、今で言う「浅蒸し製法」を指していました。ところが、1950年代後半に静岡県の牧之原台地や周辺地域で蒸し時間を長くした「深蒸し煎茶」が誕生。水色(すいしょく)が濃く、渋みや苦みが抑えられるのが特徴で、現在の煎茶の主流になりました。そのため、蒸し時間によって「浅蒸し煎茶」「中蒸し煎茶」と後付けで区分されることになったのです。
特に新茶の季節などに短時間で製茶された茶葉は浅蒸しと呼ばれ、香り高くすっきりとした味わいが特徴とされています。中蒸し茶は、浅蒸しと深蒸しの中間くらいの蒸し時間で製茶された茶葉の相対的な区分。程よい旨みと渋み、そして香りを楽しめるものが多いとされています。興味深いのは、蒸し時間に明確な決まりはなく、各製茶工場が独自の基準に基づいて、茶葉の特徴を引き出せる長さで蒸しているという点。
収穫した茶葉の状態や産地によって異なりますが、一般的には、浅蒸しは30秒以内、中蒸しは30~40秒、深蒸しは60秒以上というケースが多いようです。
また、茶葉を摘む前に茶樹を覆うことで旨み成分を増す栽培方法を施す「玉露」や「かぶせ茶」も、製法は煎茶と同様です。蒸すことで、より旨みが際立つ贅沢な一杯へと仕上がります。
日本の風土や水質に合った蒸し製法が普及・発展したことにより、日本茶には様々なバリエーションや風味の多様性が生まれ、豊かな緑茶文化に新たな広がりと可能性をもたらしたのです。

かぶせ茶と呼ばれる煎茶は1週間程度、玉露や抹茶の原料となる碾茶(てんちゃ)は20日以上、収穫前にワラや寒冷紗(かんれいしゃ)などで茶樹を覆い(被覆(ひふく)栽培)、日光をさえぎることで、旨み成分の多い味わいの新芽を育む。


蒸され柔らかくなった茶葉を、手間暇をかけて揉み込むことで、煎茶特有の豊かな味わいが生まれる。
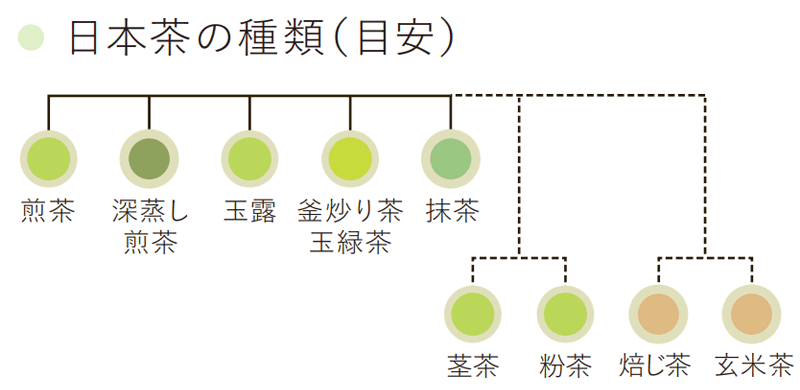
特集「炒るお茶、蒸すお茶。」目次

煎茶を極める 伝統の手揉み茶
蒸した茶葉を、加熱しながら5~6時間かけて丁寧に揉み、乾燥させて仕上げる「手揉み製茶」。濃厚で芳醇な風味は、熟練の技と長い時間をかけた手間によって生まれます。ルピシアでは、この伝統的な煎茶製法を受け継ぐ、生産量の限られた希少な茶葉を、通信販売限定で8月上旬に発売予定です。
≫ 「伝統の手揉み茶」はこちら
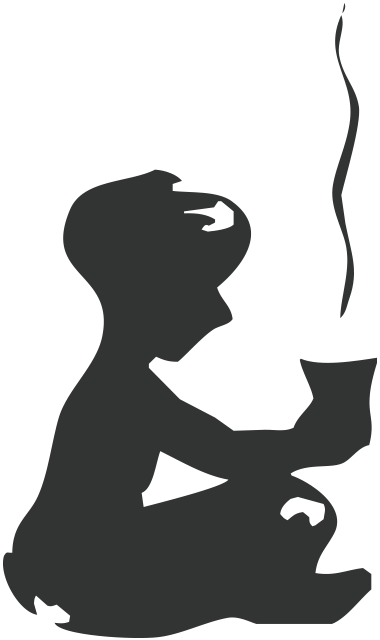 LUPICIA Tea Magazine
LUPICIA Tea Magazine