
特集「贈りもの語り。」目次
相手への敬意や感謝、そして美意識
日本では昔から「贈りもの」をするときに「包む」ということがとても大切にされてきました。これは、ただ「もの」を隠すためではなく、相手への気づかいや感謝の気持ちを表すための習慣です。
諸説ありますが、「包む」という文化の始まりは、平安時代まで遡ります。このころ、貴族たちは布や紙を使って大切なものを包んでいました。それは、物を守るだけでなく、相手に対する敬意を示すためでもありました。室町時代になると、武士たちが風呂に入る際に衣服を包むための布「風呂敷」が用いられるようになり、江戸時代には庶民の間でも広まりました。風呂敷は、「贈りもの」をむ道具としても使われ、世界でも日本の伝統的な「包装」として知られています。
日本では、贈りものを包むときに、見た目の美しさだけでなく、包み方にも意味があります。たとえば、折り方や結び方に工夫をこらすことで、贈る人の気持ちやセンスが伝わります。これば、ただ「もの」を渡すのではなく、「心を包む」ことでもあるのです。
また、包むことで物を大切に扱う気持ちも表せます。日本人は昔から「もったいない」という考え方を大事にしてきました。風呂敷のように何度も使える布で包むことは、環境にもやさしく、ものを大切にする心を表しています。
現代では、包装紙や袋など、さまざまな方法で「贈りもの」を包みますが、そこに込められた気持ちはいつの時代も変わりません。包むことで、贈る人の思いがより深く伝わり、受け取る人もその心を感じることができます。
このように、日本の「包む文化」は、贈りものを通じて人と人とのつながりを深める大切な役割を果たしてきました。包むという行為には、歴史と美しさ、そして心が込められているのです。
風呂敷と包装紙を使って、ルピシアの丸缶を包んでみました
ご紹介する2つの包み方は、さまざまな形や大きさの品物に応用ができる、手軽さと華やかさを備えたおすすめのラッピング方法です。贈りものにぜひお試しください。
飾り持ち手包み

風呂敷の「飾り持ち手包み」は、ものを包みながら、上部に持ち手を作る華やかな包み方です。まず中央に包むものを置き、巻くように包み、左右の角を交差させて結び、左右の端をねじって巻きつければ完成。見た目も美しく、贈りものにもぴったりです。風呂敷の柄や素材を使い分けることで、さまざまな雰囲気に変わります。また、風呂敷は包んで運ぶためのものと思われがちですが、ラッピングとして風呂敷ごと贈ることも多く、「飾り持ち手包み」はそれにふさわしい包み方のひとつです。
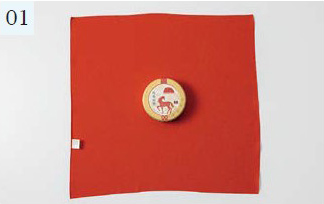
風呂敷の裏側を上にして、缶を上に置きます。

手前を缶にかぶせて、缶を
回転させながら巻いていきます。

風呂敷の奥側が、缶と同じくらいの長さになる
位置で止めます。

風呂敷の奥側を手前にかぶせます。

左右の端を持ち、1回結びます。

手前側を右の腕に巻きつけ、最後に
巻いた部分に、端を差し込んで納めます。

取手の形を意識しながら、左側も
同じように巻きつけていきます。

最後に取手を少し浮かせるように、
形を整えるとでき上がり。
しぼり包み

不織布や和紙、薄紙など、柔らかい素材の紙を使う「しぼり包み」は、難しいテクニックを必要とせずとも、華やかに見え、幅広い形状に応用することができます。
はじめに包むもののサイズに合わせて、必要な紙の大きさを決めるのがポイントです。「包むものの1周分の長さ+立ち上がりの2倍の長さ」が、包装紙の一片の長さの基本です。包装紙の種類、結ぶリボンや紐の色、素材によって、印象ががらりと変わり、和洋どちらにもふさわしいお手軽ラッピングです。
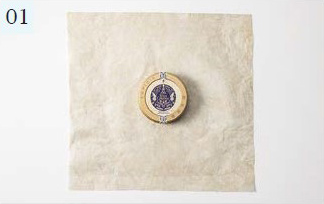
包むものの1周分+立ち上がりの2倍の
長さで、紙取りをします。

向こう側と手前の紙を立ち上げ、
缶の中央で合わせます。

合わせた紙を半分に折り、向こう側に
山折にしてつまみます。

さらに、向こう側に倒し、平らにします。

右手で缶を押さえながら、左側を
缶の縁に沿わせて立ち上げます。

立ち上げた紙を、そのまま缶の中央まで
持ってきて絞ります。

右側も同様に立ち上げ、左右を合わせて
絞ります。

絞り部分が緩まないように、しっかりと
リボンをかけて結びます。
参考:『和を楽しむ・和を贈る ふろしき包み』宮井株式会社(雄鶏社)、『ラッピングの教科書』宮岡宏会(ナツメ社)
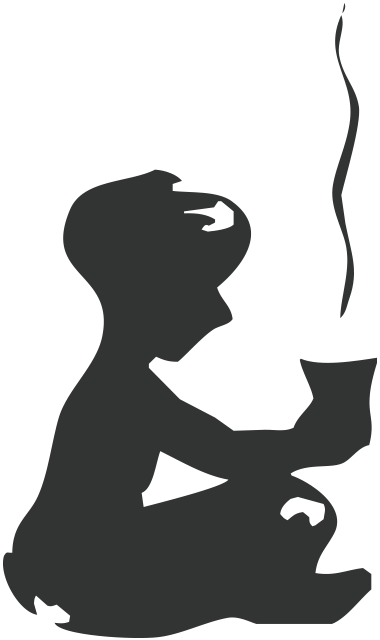 LUPICIA Tea Magazine
LUPICIA Tea Magazine