
画像:Pierre Bonnard / The Red Checked Table Cloth, or The Dogs Dinner, 1910
「言葉」の語源をご存じですか? 「言」は事象や物事と同意で「事」を表しているそうです。「葉」の字については諸説あるようですが、平安時代に活躍した歌人、紀貫之※が「古今和歌集 仮名序」の冒頭で書いた一説に心打たれます。
やまと歌は、人の心を種として、
よろづの言の葉とぞなれりける
和歌について綴られた一節ですが、自分の想いを、葉が茂るように表す。まさに「言葉」の持つ力や美しさを、語り尽くしているようです。今回の特集は「お茶のこと葉」。茶葉を語る言葉の魅力をお楽しみください。
※紀貫之 きのつらゆき(872年~945年)貴族、歌人。和歌の研究・編集・批評を行い、日本初の勅撰和歌集『古今和歌集』の筆頭選者で、三十六歌仙の一人。日本で初めてひらがなで書かれた日記文学『土佐日記』の作者でもある。
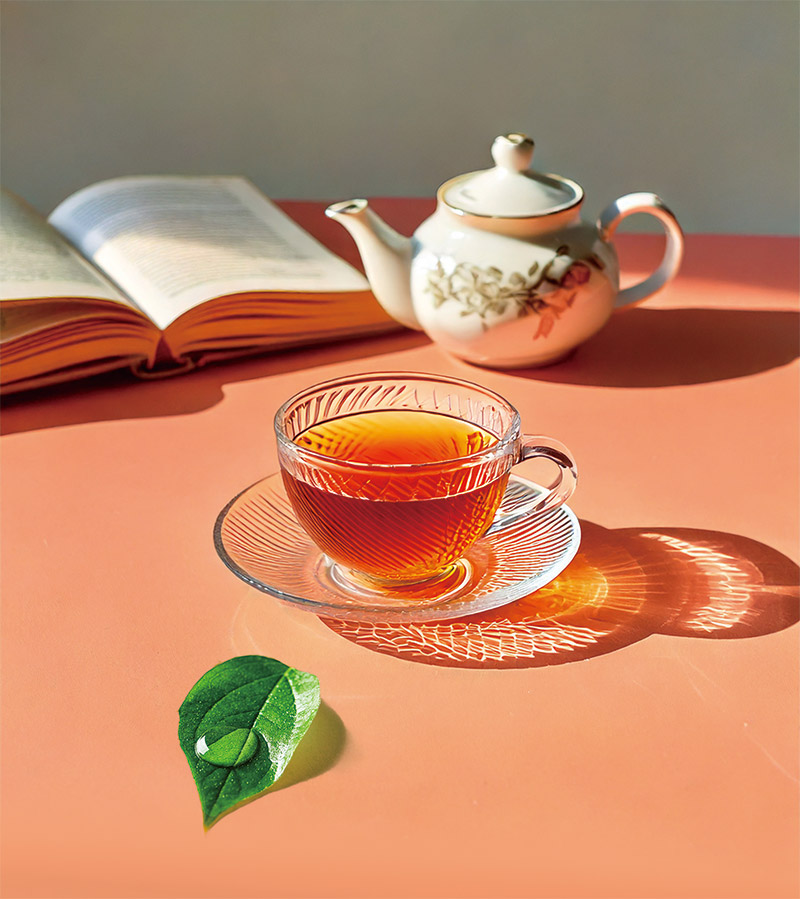
それぞれの「お茶のこと葉」
- 向田邦子
- 太宰治
- 原口統三
- 北原白秋
- 小林一茶
- 夏目漱石
- 尾形亀之助
- 宮沢賢治
- ラドヤード・キプリング
- ラビンドラナート・タゴール
- フョードル・ドストエフスキー
- ティク・ナット・ハン
- アーサー・ウィング・ピネロ
- エドモンド・ウォーラー
あまり知りすぎず、高のぞみせず、
三度の食事と仕事の
あい間にたのしむ煎茶(せんちゃ)、番茶、
そして、台所で立ったまま点(た)てるお薄(うす)。
このときをいい気分に
させてくれれば、それでいい。
『女の人差し指』文藝春秋(2011年)より抜粋
向田邦子
むこうだくにこ(1929年~1981年)
映画雑誌の編集者やラジオ番組の放送作家などを経て、テレビドラマの脚本家になる。『寺内貫太郎一家』(TBS)、『阿修羅のごとく』(NHK)、『あ・うん』(NHK)など、ありふれた日常を鋭い観察力と表現力で描き、数々の名作ドラマを執筆。『父の詫び状』を発表するなど小説家としても注目を集め、1980年に直木賞を受賞。1981年、台湾で取材旅行中に飛行機事故に遭い、51歳で生涯を閉じた。
よい仕事をしたあとで
一杯のお茶をすする
お茶のあぶくにきれいな私の顔が
いくつもいくつもうつっているのさ
どうにか、なる。
『晩年/葉』新潮社(1998年)より抜粋
太宰 治
だざいおさむ(1909年~1948年)
小説家。青森県生まれ、1930年上京。東京帝国大学仏文科中退。
井伏鱒二に師事。1935年『逆行』が芥川賞候補となる。戦後、『斜陽』、『人間失格』などを執筆、無頼派などと呼ばれた。
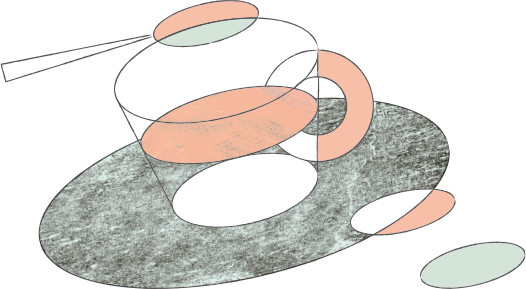
僕は、紅茶一杯でどんな夢でも見ることができた。
仲間から離れて鍵を下した一部屋で―
僕の周囲をとり巻いていたのは、数百の書物と、
汚れた白壁だけであった―
黙って茶碗のスプーンを動かしている―
この単調な動作の中から、
僕の詩集が生まれたのだった。
『二十歳のエチュード』筑摩書房(2005年)より抜粋
原口統三
はらぐちとうぞう(1927年~1946年)
旧朝鮮京城府(ソウル)生まれ。
1944年旧制第一高等学校(現・東京大学)文科類入学後、在学中の1946年逗子海岸で入水自殺。1947年『二十歳のエチュード』が遺著として刊行された。
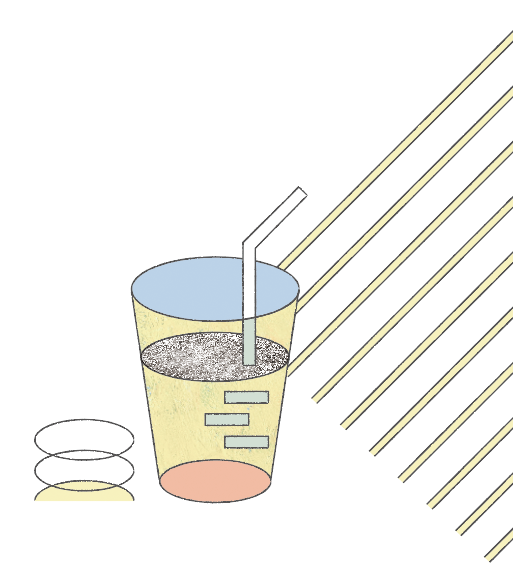
五月
新しい烏竜茶(ウーロンちゃ)と日光、
渋みをもつた紅(あか)さ、
沸きたつ吐息(といき)‥‥
さうして見よ、
牛乳にまみれた喫茶店(きっさてん)の猫を、
その猫が悩ましい白い毛をすりつける
女の膝の弾力(だんりょく)。
夏(なつ)が来(き)た、
静(しづ)かな五月(ぐわつ)の昼(ひる)、湯沸(サモワル)からのぼる湯気(ゆげ)が、
紅茶(こうちゃ)のしめりが、
爽(さわ)やかな夏帽子(なつぼうし)の麦稈(むぎわら)に沁(し)み込(こ)み、
うつむく横顔(よこがほ)の薄(うす)い白粉(おしろい)を汗(あせ)ばませ、
而(さう)してわかい男(をとこ)の強(つよ)い体臭(にほひ)をいらだたす。
「苦(くる)しい刹那(せつな)」のごとく、黄(き)ばみかけて
痛(いた)いほど光(ひか)る白(しろ)い前掛(まへかけ)の女(をんな)よ。
「烏竜茶(ウーロンちゃ)をもう一杯(ぱい)。」
『白秋全集3/東京景物詩及其他』岩波書店(1985年)より抜粋
北原白秋
きたはらはくしゅう(1885年~1942年)
詩人、歌人。1909年に第一詩集『邪宗門』を発表。1911年の抒情小曲集『思ひ出』により、詩人としての地位を確立。
1918年に『赤い鳥』の童謡部門を担当し、創作童謡を数多く発表した。生涯にわたり多数の優れた詩歌を残し、近代日本を代表する詩人とされている。
朝くや 茶がむまく成る雰(きり)おりる
しがらき(信楽)や大僧正(だいそうじゃう)も茶つ(摘)ミ唄(うた)
うぐひすも う(浮)かれ鳴(なき)する 茶つ(摘)ミ哉
新茶の香 真昼(まひる)の眠気(ねむけ)転じたり
蓮咲くや 八文茶漬(はちもんちやづけ)二八そば(蕎麦)
丸山一彦 小林計一郎
校注『古典俳文学大系15一茶集』集英社(1970年)より抜粋
小林一茶
こばやしいっさ(1763年~1828年)
俳人。一茶は俳号。信濃国柏原(現・長野県上水内郡信濃町柏原)に農家の長男として生まれる。本名は弥太郎。松尾芭蕉、与謝蕪村と並んで、江戸時代を代表する三大俳人の一人とされている。
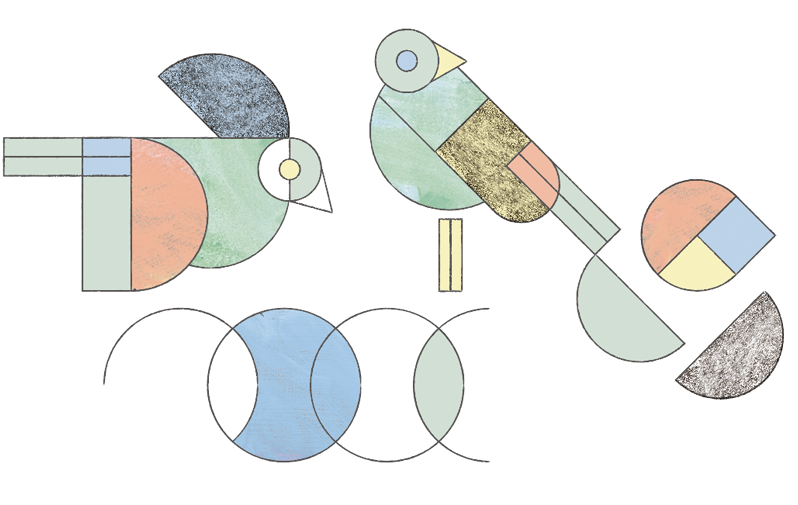
普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違だ。
舌頭(ぜっとう)へぽたりと載(の)せて、清いものが四方へ散れば咽喉(のど)へ下(くだ)るべき液はほとんどない。ただ馥郁(ふくいく)たる匂(におい)が食道から胃のなかへ沁(し)み渡るのみである。歯を用いるは卑(いや)しい。水はあまりに軽い。
『夏目漱石全集3/草枕』筑摩書房(1987年)より抜粋
夏目漱石
なつめそうせき(1867年~1916年)
小説家。1893年帝国大学英文科卒業後、松山中学、第五高校の教師を経て1900年ロンドンへ留学。『吾輩は猫である』によって文壇に登場後、1907年朝日新聞社に入社し専属作家となった。『三四郎』『それから』『門』などを発表した後は、大病を経て『こゝろ』などの作品で近代知識人の内面を描き、近代日本の代表的作家とされる。
わたしビールのむ、
お茶のむ。毒のまない。
これながいきの薬ある。
のむよろしい。
『山男の四月』草の根出版会など、より抜粋
宮沢賢治
みやざわけんじ(1896年~1933年)
詩人、童話作家。農業指導者として農民生活の向上に尽くす傍ら、東北地方の自然や生活を題材に詩や童話を執筆。1924年詩集『春と修羅』、童話集『注文の多い料理店』を自費出版。作品中に登場する架空の理想郷に、郷里の岩手県をモチーフとしてイーハトーブと名付けた。37歳で病死。
私 私はそのとき
朝の紅茶を飲んでいた
私の心は山を登る
そして
私の心は少しの重みをもって私についてくる
『美しい街』夏葉社(2017年)より抜粋
尾形亀之助
おがたかめのすけ(1900年~1942年)
詩人。宮城県柴田郡大河原町生まれ。1920年東北学院中学中退後、上京。主な作品に『色ガラスの街』『雨になる朝』『障子のある家』がある。
やかんがあったのに、
水漏れさせてしまった:
私たちが修理しなかったせいで、
さらにひどくなった。
この1週間、お茶を飲んでいない。
宇宙の底が抜けた!
『The Works of Rudyard Kipling 1994』より抜粋
ラドヤード・キプリング
Joseph Rudyard Kipling(1865年~1936年)
イギリスの詩人、小説家。大英帝国統治下のインド・ポンペイ生まれ。1907年にイギリス人初のノーベル文学賞受賞。主な作品に『ジャングル・ブック』『ゾウのはなはなぜ長い』など。
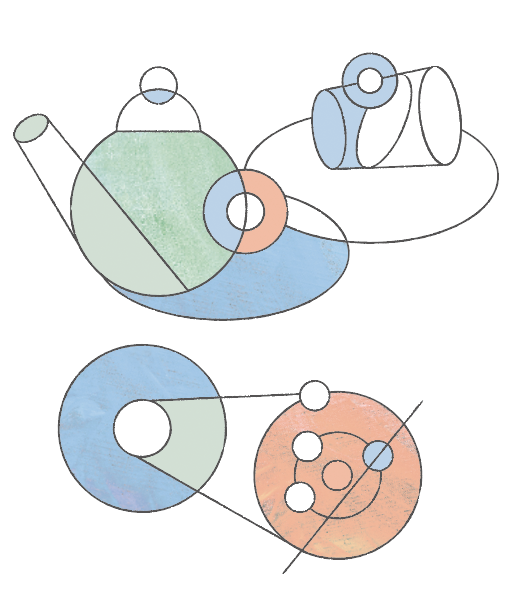
さあさあ、お茶に飢えた落ち着きのない者たちよ。
やかんが沸騰し、泡立ち、音楽的に歌う。
Sara Tabandeh著『Voices of Wisdom: Rabindranath Tagore Quotes』より抜粋
ラビンドラナート・タゴール
Rabindranath Tagore (1861年~1941年)
インドの詩人、小説家、思想家。インドの近代化を促し、東西文化の融合に努めた。1913年、アジア初のノーベル文学賞受賞。代表作に詩集『ギーターンジャリ』、小説『ゴーラ』など。
世界が消えてなくなるのがいいか、
それとも、お茶が飲めなくなるがいいか?
答えてやるさ、
世界なんて消えてなくなったっていい、
いつも茶が飲めさえすりゃ、ね。
[新訳]『地下室の記録』集英社(2013年)より抜粋
フョードル・ドストエフスキー
Fyodor Mikhaylovich Dostoevskiy(1821年~1881年)
小説家。処女作『貧しき人々』で作家として出発。混迷する社会の諸相を背景として、内面的、心理的矛盾と相克の世界を描き、人間存在の根本的問題を追求。20世紀の文学に多大な影響を与えた。代表作に『罪と罰』『白痴』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』など。
地球全体が自転する軸であるかのように、
ゆっくりと恭しくお茶を飲みなさい。
ゆっくりと、均等に、未来に向かって急がずに。実際の瞬間を生きる。この実際の瞬間だけが人生なのだ。
『The Miracle of Mindfulness: An Introduction to the Practice of Meditation』Beacon Press(1996年)より抜粋
ティク・ナット・ハン
Thich Nhat Hanh(1926年~2022年)
ベトナム生まれの禅僧、平和運動家、学者、詩人。ダライ・ラマ14世と並び称される世界的な仏教者で、マインドフルネスの提唱と普及に努め、ノーベル平和賞の候補にも選出された。著書多数。

お茶があるところには希望がある
『Sweet Lavender : A Comedy in Three Acts』W.H. Baker & Company (1893年)より抜粋
アーサー・ウィング・ピネロ
Arthur Wing Pinero (1855年~1934年)
イギリスの劇作家。俳優として出発し、1877年に最初の戯曲を発表。戯曲『Sweet Lavender』は、1888年に初演された愛と結婚をテーマにした3幕の喜劇。長い上演歴を持つことから、彼の代表作の一つとされている。80年代から90年代のイギリス劇壇を代表する笑劇作家となり、1909年に劇壇への貢献によってサーの称号を与えられた。
ヴィーナスが身にまとう
テンニンカ(マートル)
アポロが冠る月桂樹
そのいずれよりも茶は素晴らしい
女王は茶をめで下賜賜う
角山栄著『茶の世界史』中央公論新社(2017年)より抜粋
エドモンド・ウォーラー
Edmund Waller(1606年~1687年)
イギリスの政治家、詩人。一般的に英国に茶を紹介したのは、1662年にチャールズ2世の妃となったポルトガル王の娘、キャサリン・オヴ・ブラガンザであるとされ、エドモンド・ウォーラーは、「王妃陛下に推奨された茶について」と題された詩を書いた。Edmund Waller, “Of Tea, commended by Her Majesty,” The Second Part of Mr Waller’s Poems (London: T.W., 1705)。
この小品の制作年代は不明だが、上記詩集の初版(1690年)に初めて収められた。

特別企画「あなたのお茶のこと葉」作品公募
募集は終了しました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
2025年5月22日から6月30日までの期間に、応募総数164件、合計278作品をご投稿いただきました。今回集まった「お茶のこと葉」は、それぞれが日常の風景や人々のつながり、体験や実感などが込められた印象深いものでした。中でも特に印象に残った19作品について、この場をもって公表させていただきます。
≫ 作品発表についてはこちら
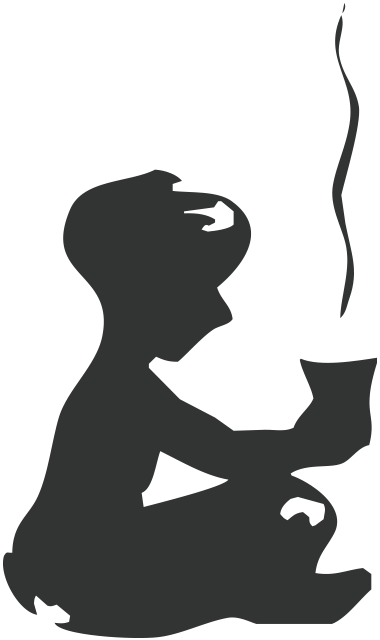 LUPICIA Tea Magazine
LUPICIA Tea Magazine